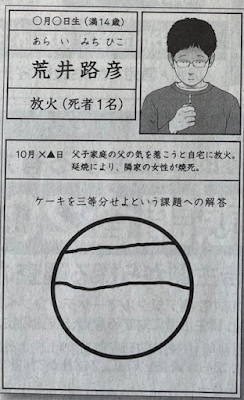元プロレスラーのアントニオ猪木さんが昨日亡くなった。子どもの頃、毎週金曜日と水曜日夜8時からのプロレス中継を見て育ったわれわれ世代にとっては、大きなショックだ。残念だ。1999年にジャイアント馬場さんがなくなり、寂しい思いをしていたのに追い打ちを掛けられたような気分だ。
彼は2020年、難病の「心アミロイドーシス」という病におかされ闘病生活をしていることを自身で明らかにし、闘病するそのベッドからも最後の姿をYouTubeで発信し続けていた。
今朝は、毎日新聞、東京新聞、日経新聞のそれぞれの一面コラムで猪木さんが亡くなったことが書かれていた。書き手が、たぶん僕と近い世代なんだな。
プロレスというのは面白い競技だと思う。例えばプロボクサーは勝たなければ名前が上がらない。プロテニス選手も、プロゴルファーも優勝しなければ次へつながらない。だが、プロレスラーは必ずしもそうではない。リング上で観客の笑いを取り、力や技では相手選手に適わないにもかかわらず、それ以上の人気をはくす選手がいた。
プロレスは格闘技スポーツだが、ショービジネスとしてのエンターテインメント性も不可欠だ。「これ一本きり」では済まない。プロレスという競技がそうだけでなく、猪木自体もレスラーであり、プロモーターであり、経営者であり、そして参議院議員だった。そんなマージナルな存在にずっと引かれていたのだと、いま僕は気がついた。
10年ほど前、ニューヨークで猪木さんと至近距離で遭遇したことがある。当時、僕はマンハッタンのアッパー・ウエストサイドに住んでいた。ある日、1階に着いたエレベータから降りようとしたら、目の前に彼がすっくと立っていた。スーツに赤いネクタイ。そして、トレードマークの赤いタオルを首にかけていた。ちょっと疲れた、そしていくぶん寂しげな表情だった。その時、彼に連れはいなかったと思う。そこにNY滞在用の部屋を持っていたんじゃないかな。
あんな元気で、尖っていて、発信力のある人はそうそう出てこない。カッコよかった。1976年にはボクシング世界ヘビー級チャンピオンのアリと闘うなど、チャレンジ精神の塊だった。
ひとつの時代が終わってしまった。またあの「元気ですかーっ!」の声が聞きたい。