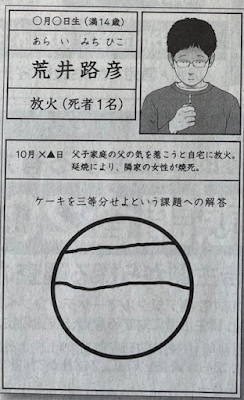医師中村哲さんのパキスタン、アフガニスタンの活動を追ったドキュメンタリー映画を観るため、横浜のシネマ・ジャック&ベティへ。
中村さんは32歳の時に登山隊の一員としてパキスタンを訪れたことをきっかけに、3年前に不慮の死を遂げるまで実に35年間にわたってパキスタンとアフガニスタンで医療と現地の人びとの生活を支える支援を続けてきた。その彼を日本電波ニュース社のカメラマンが20年以上にわたり映像におさめていたものがこの映画だ。
中村さんの素晴らしい、ずば抜けた活動は何冊かの書籍になっているし、また映像(DVD)にもまとめられているので、あらためてここに書く必要はないだろう。
ただ僕が心打たれたのは、彼がパキスタン、アフガンの支援を続ける理由を問われたとき「見捨てちゃおけないからという以外に、何も理由はないです」と答えていること。それは嘘でも衒いでもない、彼の心からの気持ちだと感じた。
最初、現地の医療支援のために行ったわけでもないところで、医療を必要としていながら見捨てられた人たちに出会って、自然と自分の役割が自分のうちに芽生えたということか。
発展途上国の人たちを救うことが正義だからとか、神の教えに沿って人助けを始めたとかではない。もっと基本のところ、誰もが人間として持つ倫理観からだ。
その後、彼は医者として人びとを救う傍ら、その地域で人びとが生き続けられるようになるには農業を続けることが不可欠であり、そのためには農業用水の確保が必須であると知る。その後は、自らが先頭に立ち灌漑工事を始めることになる。一から土木技術を学びながらだ。
その結果、砂漠だった地に水を引き入れ、赤茶けた土地を緑の大地に変えていったのである。
 |
| スランブール地区は、5年で緑の作物一面に変わった(before/after) |
 |
| ガンベリ砂漠には10年かけて畑と防風林ができた(before/after) |
以前、「マラリア・ノーモア・ジャパン」の事務局長をしていた水野達男さんと対談した折、彼がアフリカのマラリア撲滅を目指して活動を始めたきっかけは、当時工場建設のために赴任していたアフリカの地で、マラリアが原因で子どもをなくした母親が打ちひしがれている姿を路上で見たことだと聞いた。
目の当たりにしたその姿に「このままじゃいかんな」という怒りのような気持ちがフツフツと沸いてきたという。それをきっかけに、彼は大手化学会社のビジネスマンを辞めてNGOの活動に専念することになった。
「このままじゃいかんな」という理屈を越えた感情が彼の残りの人生を変えた。「見捨てちゃおけないから」という中村さんのシンプルな気持ちと同じだ。
僕たちは自宅にいながらパソコンやスマホでどんな情報でも手に入れられ、それによって世の中のこことを分かった気になり過ぎているかもしれない。知るだけじゃなく、感じることが必要なんだ。そして、それに時に正直にしたがい、自分を動かしていくことが不可欠ではないかと中村さんと水野さんに教えられた気がした。